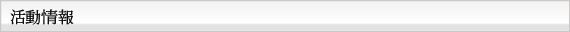 »活動情報一覧
»活動情報一覧
カテゴリ: 活動情報 >雑誌・新聞掲載・出版
2010.1.19信濃毎日新聞【文化面】東山魁夷が選んだ風景・ドイツ・オーストリア編①
「霧の町リューベック」孤独な魂が潜む寂寥感
1 霧の町(リューベック)
戦争の足音が聞こえてくる1933年、東京美術学校(現・東京芸大)研究科を終了した25歳の東山魁夷はドイツに渡る。ナチスが第一党になり、ヒットラーが首相に就任した年である。魁夷はベルリン大学哲学科に入学し、美術史を学ぶかたわら、美術館に足しげく通う。画家、東山魁夷の誕生は、この2年間の留学生時代を抜きには語れない。
35年後の1969年、日本の代表的画家になった魁夷は、4ヶ月に渡って、第二の故郷と呼ぶドイツとオーストリアを巡る。この旅で描いた作品群には東山魁夷を理解する鍵が潜んでいる。それから40年を経過した昨年、私は魁夷の足跡を追った。
還暦を過ぎた魁夷が最初に訪れたのがドイツのリューベックだ。13世紀、14世紀頃、北ヨーロッパの海上貿易を独占していたハンザ同盟の盟主だったこの町は「バルト海の女王」と謳われた。現在、旧市街は世界遺産に登録され、世界各国からの観光客でにぎわっている。
この「霧の町」は、リューベックの象徴とも言われるホルステン門を右上に描く。私は、絵とほとんど同じ写真を、教会の塔の上から望遠レンズで撮影することができた。ということは、魁夷自身も同じ場所から写真を撮ったと考えられる。スケッチだけではこれだけ正確な描写は不可能である。しかし、絵と写真では構図こそ同じだが、醸し出す雰囲気はまったく異なる。
魁夷は青春時代、トーマス・マンの「トニオ・クレーゲル」に深く共感していた。この小説はマン自身が投影された作品であり、芸術家としての苦悩と市民の生活が対比されながら展開する。魁夷は、ものを作り出す人間の孤独を描いたこの小説を自分自身に重ねて読み、舞台となったリューベックの街並みは心の中に描きこまれていたという。魁夷はこんな一文を残している。「(リューベックは)マンの郷愁の世界の象徴としての町であり、私にとっては、ことに、霧の中の幻影のようなものであった」。
「霧の町」に感じられる寂寥感は芸術家の孤独な魂がそこに潜んでいるからだろうか。この絵はトニオ・クレーゲルが歩き回っていた20世初頭のリューベックを描いているように思えてならない。
活動情報雑誌・新聞掲載・出版:新着記事から5件
- 2025.02.10
- 【新刊チラシ】2/27刊行「絵本とは何か」
- 2025.02.10
- 【講演】3/8「絵本の今とこれから」
- 2024.10.28
- 子どもの文化
- 2024.10.24
- 【講演】11/10「子どもの幸せと平和を描き続けた ちひろの世界を語る」
- 2024.10.06
- 【特集記事】東京新聞
- 2025.02.10
- 【新刊チラシ】2/27刊行「絵本とは何か」
- 2025.02.10
- 【講演】3/8「絵本の今とこれから」
- 2024.10.28
- 子どもの文化
- 2024.10.24
- 【講演】11/10「子どもの幸せと平和を描き続けた ちひろの世界を語る」
- 2024.10.06
- 【特集記事】東京新聞
- »活動情報一覧
- 2018.04.08
- 高畑勲さん亡くなる
- 2018.01.05
- あけましておめでとうございます
- 2017.12.27
- 今年もあとわずか
- 2015.03.14
- 新しい絵本を出版しました。
- 2014.04.30
- 憲法と秘密保護法は両立するの?
- »つれづれ日記

ケータイでもご覧いただけます。
左のQRコードを読み込んでください。うまく読み込めない場合は下のURLを直接入力してご覧ください。

